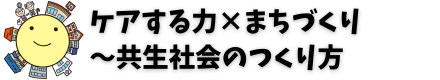ツールの紹介
N-impro
N-impro (ニンプロ)は、地域住民として、地域に暮らす高齢者や認知症のある方への対応を考えるためのツールとして開発した対話型カードゲームです。2017 年に東京都練馬区における産官学協働プロジェクトの取り組みから生まれました。参加者はカードで提示される高齢者に関するさまざまな状況について、他の参加者との意見交換を通して、場面に応じた行動や自分にできることを考えます。このゲームの目的は、正解を選ぶことではなく、話し合いを通じて状況に応じた対応を考え、模索することにあります。N-impro への参加により、認知症のある人に対する態度や地域貢献に関する意識が改善するという効果が研究によって検証されています(Igarashi et al.,2020) 。
高齢になっても住み慣れた地域の中で安心して暮らし続けられる社会の実現を目指し、N-impro をさまざまな年代や立場の方に実施していただくことで、地域での高齢者支援のネットワークを広げていくきっかけにしていきたいと考えています。
小学生版N-impro も作成しています。詳しくはこちら からご覧ください。
N-improの3つのねらい
学ぶ :認知症をはじめとする、高齢者の心身の特徴と地域にあるサービスや対応方法について、楽しみながら学ぶ。つながる :まちに関係するさまざまな人と一緒にゲームをすることで、今度何か困りごとが起きた時に相談や連携しやすいような関係性を築く。考える :他の人の味方や考え方をヒントにしながら、簡単に答えの出ない難しい課題を、立場や仕事の枠を超えて共に考える。
N-improのすすめ方
1テーブル5~7名程度(奇数での実施が望ましい)で行います。司会者(ファシリテーター)が各テーブルに1名つき、進行役を務めます。
司会者が「状況カード」を読み上げます。
提示された状況に対し、参加者はYES・NO どちらかのカードを選び、裏返しにしてテーブルの上に出します。そして、司会者の合図で全員一斉にカードの答えを見せ合います。
多数派の回答には得点カード(大根カード:1点)が配布されます。ただし、少数派が一名だった場合には、その一名にのみ特別カード(おでんカード:3点)が配布されます。
その後、YES・NO のカードを選んだ理由について、参加者同士で話し合います。
以上の一連の流れをカードの実施枚数分行い、総得点の多い人が勝ちとなります。
VIDEO
参考資料
Igarashi A, Matsumoto H, Takaoka M, Kugai H, Suzuki M, Yamamoto-Mitani N. Educational Program for Promoting Collaboration Between Community Care Professionals and Convenience Stores. J Appl Gerontol. 2019 Sep 3;39(7):760-769. N-impro の開発およびその効果検証について報告した論文です。地域のケア専門職とコンビニエンスストアの従業員が協働し、認知症の高齢者への対応能力を高めることを目的とした教育プログラムの成果を示しています。近藤尚己, 五十嵐歩, 編. 認知症plus 地域共生社会:つながり支え合うまちづくりのために私たちができること.東京: 日本看護協会出版会; 2022. N-impro の開発背景と実践事例を紹介しています。東京都練馬区における産官学連携プロジェクトや、中学校で実施された認知症サポーター養成講座におけるN-impro の活用事例について解説しています。五十嵐歩, 髙岡茉奈美, 宮澤信周. 高齢者教育を通じた地域づくりの取り組み―小学校と医療・介護専門職の連携.コミュニティケア. 2024 Nov;26(12):36-40. N-impro を用いた教育実践を紹介しています。地域の医療・介護専門職と連携し、実施された授業内容を解説しています。澤陽子, 松本博成, 井垣美佐子, 植田智恵子, 牛山博志, 大竹徳明, 織田つや子, 神美保, 直嶋美和子, 野中論子, 本間雅未, 丸地由美子, 久保智子, 鈴木はるの, 高岡茉奈美, 久貝波留菜, 五十嵐歩 会えなくても地域をつなぐ「 オンラインN-impro」.コミュニティケア.2022 Jul;24(9):38-41. N-impro の実践について紹介しています。対面での集まりが難しい状況でも、認知症に関する学びの機会を確保し、地域のつながりを維持することを目的に、練馬区大泉圏域の地域包括支援センターの専門職とともに取り組みました。五十嵐歩, 髙岡茉奈美, 松本博成, 鈴木はるの, 山本則子. 認知症フレンドリー社会の創成に向けた多様なイニシアチブの活動 実践報告(22) Dementia-Friendly Community 実現に向けた認知症啓発ツールの開発と実装の試み:子ども向け学習プログラムの作成.老年精神医学雑誌.2023 Aug. N-impro を参考に、低学年向けの状況カードを作成して活用しました。小学生版N-impro の作成と実践につながる取り組みの一つです。